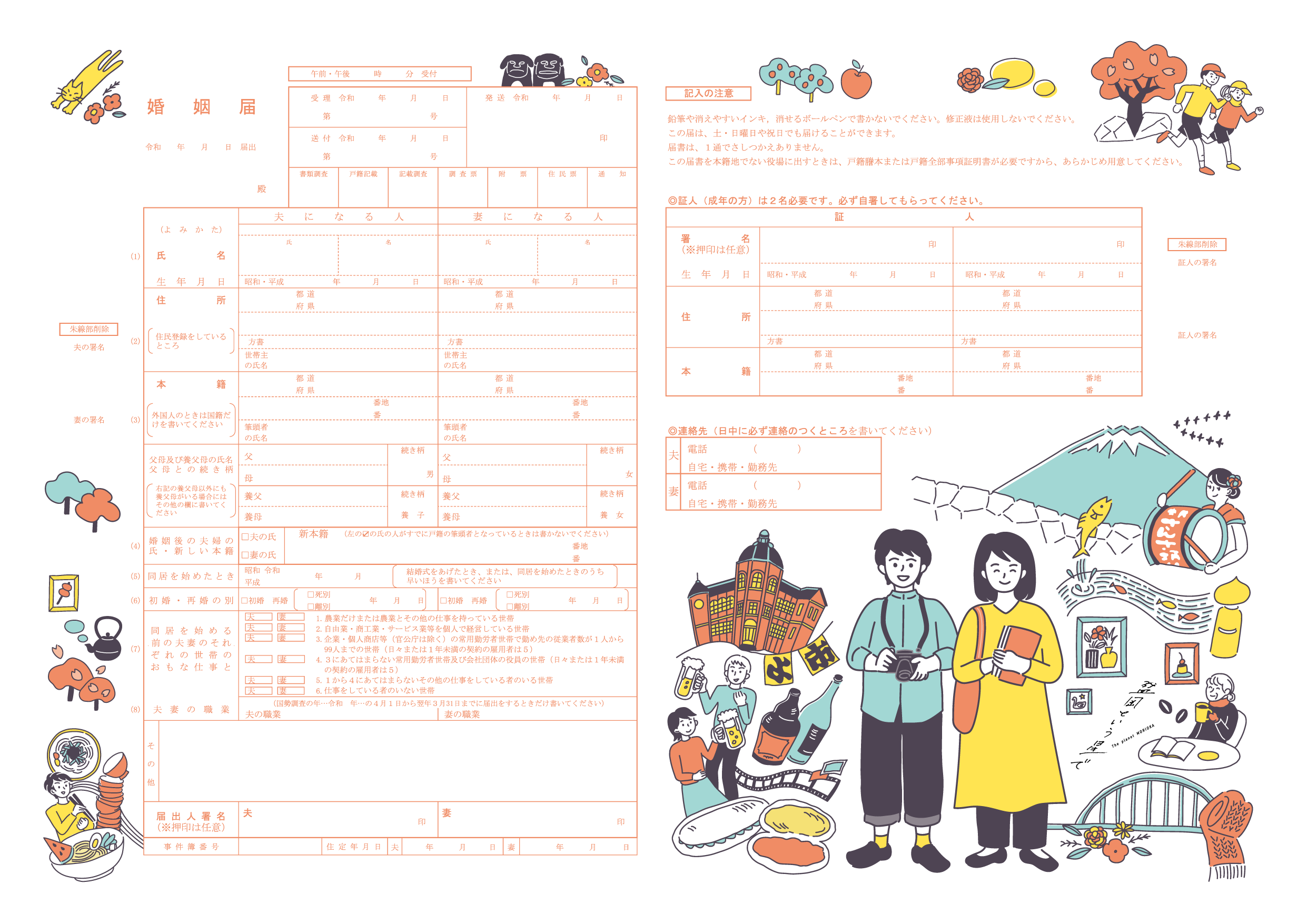こんにちは。先日リトルもりおかに仲間入りした新米ライターのすなです。
今回は盛岡本ブックレビュー第5弾として、第165回芥川賞候補作である「氷柱の声」(くどうれいん)をご紹介します。著者のくどうれいんさんは岩手県盛岡市出身、そして在住の作家さんです。
「氷柱の声」のあらすじ
本作は東日本大震災の発生当時に高校生だった主人公・伊智花(いちか)と、その友人や知人たちが震災での経験について悩み、葛藤する物語です。盛岡市出身で震災体験者である主人公が、10年に渡る日常のなかで様々な友人や知人と関わり、自分自身の思いやアイデンティティを少しずつ形成し、生きていく様子が描かれます。
美術部に所属している伊智花が、高校生活最後の絵画コンクールに向けて滝の絵を描く場面から物語は始まります。その後、仙台で大学生活をはじめた伊智花にできた友達のトーミは、福島出身で震災をきっかけに医師になることを目指していますが、そんな自分の将来の選択に疑問を持つようになります。伊智花の恋人である中鵜も宮城で震災を経験しており、今でもろうそくの火を直視することができません。
著者のくどうれいんさんは本書を執筆するにあたり、岩手、宮城、福島にゆかりのある20代の7人に話を聞いたそうです。実際の声を聞いて執筆したからこそ滲み出るリアリティが、この小説からは感じられます。

それぞれのあの日と向き合う物語
「氷柱の声」は盛岡市の高校に通う主人公の伊智花を中心として、様々な形で震災を経験した人々と出会い、交流していく話です。この本を読み始めてすぐに「これは自分の話だ」と錯覚するほどリアルな日常が綴られています。小説として出版された本書ですが、淡々と進む日常の描写がまるでエッセイやドキュメンタリーのようです。
自分自身のあの日を振り返ると、私は震災当時高校三年生で卒業式を終え、3日後に高校の友人と卒業旅行を計画していました。母親と盛岡駅まで買い物に行こうとして外に出たところ地震は起こり、長くて大きい地震だとなんとなく感じていたものの、あんなに甚大な被害をもたらすものだとは全く思っていませんでした。伊智花と同じように、数日間の停電から復旧したあと、初めてつけたテレビでやっと被害の大きさを知ることになります。
そして伊智花と同じように自分自身が決定的な被害を受けなかったということと、この震災によって多くを失ってしまった人がたくさんいることに罪悪感を覚えることもありました。自分が悲しんだり傷ついたりすることは筋違いなことだと思ってしまう伊智花に、自らの気持ちが重なります。この物語を読んで、自分が出身地を語る時に言い訳のように出てくる「私は全然被害を受けていないんですが……」という枕詞をふと思い出しました。
本書の中で、伊智花はこんなことを思います。
『そもそも、内陸でほとんど被害を受けていない私が何かを描くのもとても失礼な気がした』
この文章を読んだとき、被害を受けていないことに罪悪感を覚える伊智花が、自分の声を代弁してくれているような気がしました。そして同時に被害を受けていない私が傷つくことはおかしいと、自分の気持ちに向き合うことを避けていたことに気付きました。
私は心のどこかで自分を「傷ついてはいけない人間」だと思っていました。でも本当はあの日からそれ以降のことを思い出すのは未だに苦しく、小さいけれど確かに心の傷として残っています。今も緊急事態速報の音が苦手で、スマホから一斉にあの音が鳴ると一瞬のどが詰まり、冷や汗が出ます。
震災に限ったことではなく、私たちは無意識に自分以外の誰かと比べて自分の感情を否定することがあります。「自分はあの人より恵まれている」「もっと頑張っている人がいる」「もっと大変な人がいる」と勝手に自分の気持ちに蓋をすることがあります。けれど自分が感じている気持ちを誰かと比べる必要はなくて、本当はそれぞれが感じたまま受け入れていいはず。この本を読み終わったとき、そんなメッセージを受け取ったように思います。

「誰かの期待」というフィルター
本作では、感動的に語られる「震災モノ」に対する違和感が描かれています。著者が「震災を、社会が求める感動物語にしない」ことを意識して本作を執筆したことが伝わります。この物語に登場する人々はただ日常を生きているだけです。それが震災というフィルターを通すだけで全てドラマティックな物語になってしまうことへの抵抗感が示されます。
被災した人たちが震災に負けず前に進む、希望の物語を見たいという願いや期待は、時に飾らない本当の姿や事実を覆い隠します。しかし一人ひとりをよく見れば、傷の深さも形もその後の生き方も違うはず。本作ではこういった社会の「無意識の偏見」があぶり出され、はっきりと感じていたわけではないけれど、どこかで抱いていた違和感が浮き彫りになります。
震災を風化させずに未来に伝えていくために、ドラマティックな物語やエピソードが担う役割もある。けれど同時にそこには日常があり、日々の暮らしと地続きであるという当たり前のことをこの物語は思い出させてくれます。
社会と関わる以上、「誰かの期待」というまなざしを受けずに生きるというのは難しいことです。けれどそれに応えたいと思って生きることも、応えず自分の思うままに生きることも間違いではなくて、ありのままの自分でいることを肯定してくれるような作品になっています。
本書はそれぞれの立場から読むことで、違った意味を持つ物語です。きっと読み終わったときには、一人ひとりの心に寄り添ってくれると思います。
【参考図書】
氷柱の声
著者:くどうれいん
レーベル:講談社
文:すな